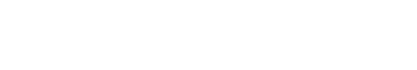電装系の心臓部分であるバッテリー
ここ近年のバイクの傾向として、電装系装備の充実があります。
大きな転機となったのはエンジンへの燃料供給システムにキャブレターではなくインジェクションシステムが導入されるようになったということです。
現在ではクラッチ操作やブレーキ効果なども伝送機器によって細かく制御をされるタイプのバイクが新車として次々に登場しています。
それだけにバイクにおけるバッテリーの重要性は高まってきており、日常点検もしっかりしておく必要があります。
バイク用バッテリーは大きく二種類があり「開放型」と「MT(メンテナンスフリー)型」とされています。
開放型は定期的にキャップを開けてそこからバッテリー液を補充しなければならないという手間がありましたが、密閉型のMT型バッテリーが主流になってきたことによりかなりメンテナンスの手間は楽になりました。
今後バッテリーを交換するという場合そのほとんどがMT型となると思いますので、MTバッテリーの整備方法について説明をしていきます。
MTバッテリーの場合、黒いカバーで覆われた四角い箱状をしており上部にはプラス端子とマイナス端子の2つのプラグのみがつけられています。
バイクの場合ほとんどの車種でシートの下に固定されているので、まずはそれぞれの車種の手順に従いバッテリーが搭載されているカバーを開いてみましょう。
交換基準は10,000km走行または12ヶ月ごと
一般的なMFバッテリーの交換の目安となるのは、10,000km走行時もしくは前回交換から12ヶ月が経過したタイミングです。
しかし最近はバッテリー性能がかなり高くなってきており、長寿命バッテリーとして販売されている製品もあるため基準は一律に定まっているというわけではありません。
上手に乗ればバイクバッテリーは5~7年くらい持たせることができるとされているので、使用頻度によって交換時期は見極めていきましょう。
バッテリーの交換はバイク用として販売されている新しいバッテリーを用意しておき、まるごと交換することで行います。
端子部分はネジでコードが止められているので、必ずマイナス端子側から外し、取り付ける場合もプラスから行うようにします。
このときただ交換をするのではなく、先に外したバイク本体についたコード接続部の金具をキレイに清掃しておきましょう。
バッテリー性能は高くなったとはいえ、電力を伝達するという構造から接続部に汚れがあると機能を十分に発揮することができません。
バッテリー交換時期でなくとも端子部分をキレイにするだけで機能が復活することもありますので、ロングドライブなどをして内部の汚れがついたあとにはバッテリー端子部分を清掃しておくことをすすめます。