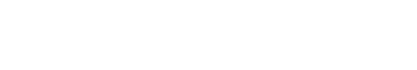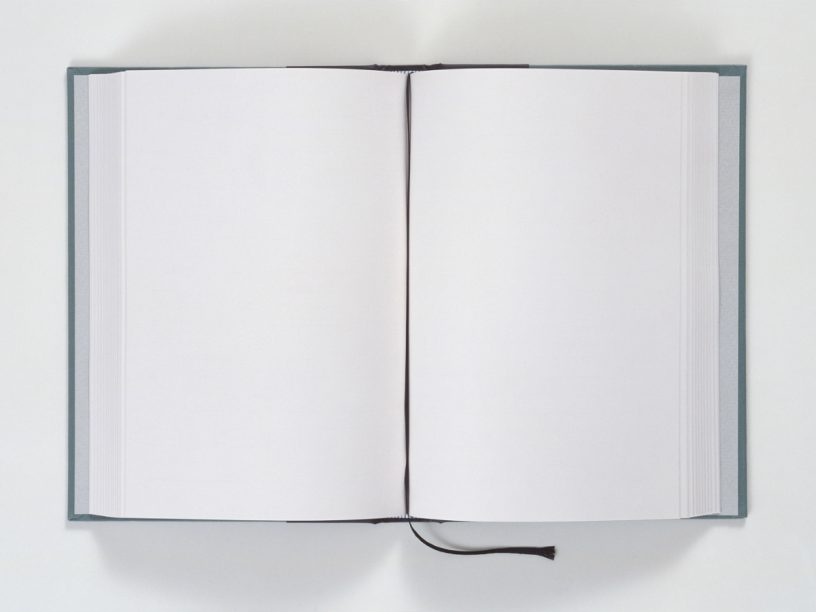街乗りに最も便利な原付2種のための免許
バイクの免許制度が始まったのは昭和44年(1969年)からのことです。
小型限定という区分ができたのは昭和50年(1975年)からで、以降バイクの区分は「原付」「小型限定」「中型限定」「限定なし」として管理施行されていきます。
その後平成8年(1996年)には「中型限定」「限定なし」が廃止となり、現在のような「普通自動二輪車」「大型自動二輪」となります。
直近の大きな改正としては平成17年(2005年)にバイクにもAT制度が導入されることとなり、それから10年余の間このときに定められた全7種類でバイクの免許は管理されています。
小型限定普通二輪免許はここ近年非常に注目を受けている分野であり、普段の街乗りに非常に使い勝手のよい原付2種に乗るための免許区分となっています。
小型限定普通二輪免許には二種類があり、通常のMT車を含む全ての小型バイクに乗れる免許と、スクータータイプとしてAT限定で乗れる免許とに分けられます。
ちなみに原付2種とされるバイクはナンバープレートがピンク色になっているところに大きな特長があり、通常の50cc以下の原付1種は黄色なのですぐにバイク区分が判断できるようになっています。
現在この原付2種も自動車免許を取得すれば自動的に乗れる制度にしようという運動もあるのですが、なかなか実現までの道のりは遠いようでここしばらくは現行制度通りに実技試験と筆記試験が必要な免許試験が行われていくことでしょう。
小型限定普通二輪免許を取得するための方法
小型限定普通二輪免許以上のバイク免許取得方法はだいたいみな同じで、試験場で直接即日試験を受ける「ダイレクト受験」と、教習場で必要な教習を修了する受験方法とに分けられます。
ただしダイレクト受験での合格率は非常に低いので、無免許もしくは原付免許しか持っていない人がぶっつけ本番的に行っても合格できる確率は非常に低いでしょう。
より確実に取得をするには教習所で技能教習と学科教習を受け、そこで卒業検定に合格してから運転免許試験場で免許を申請するというのが楽な方法になります。
小型限定普通二輪免許を受験するための条件は原付同様に16歳以上であるということと、視力、色覚、運動能力、聴力が適正であることです。
本試験の前には適性試験が行われることになっているので、そこで合格をしたのちに筆記試験などを受けます。
指定教習所としての認定を受けている学校なら、そうした適性試験は教習所で行うものとして本試験会場では免除となることもあります。
先に教習所で必要な教習を修了した人の場合、当日の運転免許試験場での試験にかかる費用は4000円程度ですが、ダイレクト受験として受験する場合には2万円以上が1回につきかかります。